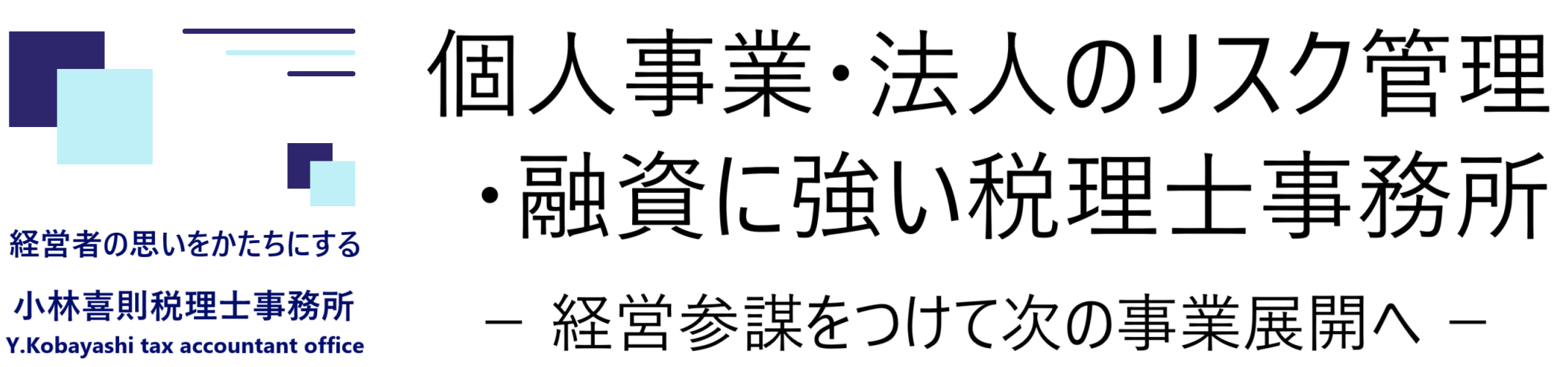知らないと税金を損してしまうケース
税金の確定申告に際しては、個々人の事情を考慮する目的で設けられた所得税の規定が、ご自分に適用可能な制度かどうか検討をすることで、余計な税金の支払いを避けることができます。
今回のコラムでは、こうした確定申告において税金の納付金額に影響を及ぼす、見逃しがちなケースのいくつかを取り上げてみたいとおもいます。
配偶者と離婚・死別した場合
所得税法は夫婦の所得に応じ、一方の所得から一定金額の配偶者控除・配偶者特別控除を認めていますが、年度の最後・12月31日時点で法律婚の現況にあること又は死別であることが条件です。
では、年度の途中で夫婦が離婚などをした場合には、確定申告で所得から控除できる規定が所得税法に、何か設けられているのでしょうか。
ひとり親控除
合計所得金額500万円以下の人が、法律婚関係にあった配偶者と離婚又は死別した後、再婚せずに同一生計の子ども(総所得金額48万円以下)を育てている場合には、35万円のひとり親(男親も可)控除が認められています。
合計所得金額が48万円以下の配偶者と死別した場合、その死亡年度分についてはひとり親控除と併せて配偶者控除も受けられる可能性もあります。もちろん子どもの扶養控除も、子の年齢により受けられます。
寡婦控除
合計所得金額500万円以下の女性で、法律婚関係にあった配偶者と離婚又は死別した後、次のいずれかに該当する人は、27万円の寡婦控除を受けることができます。「寡婦」ということから、男性に適用はありません。
(1) 配偶者と離婚後、未婚のまま母親などの親族を扶養している女性
(2) 配偶者と死別後、未婚のままの女性
iDeCoで年金を運用している場合
投資先の一つとして、また節税としてiDeDoにより確定拠出年金を運用している方が増えていますが、自営業の方は年間816,000円、会社員や専業主婦の方は年間276,000円まで掛金を拠出することができます。
所得税法上、確定給付企業年金の掛金が「生命保険料控除」の対象となるのに対し、確定拠出年金の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となっています。
掛金の全額が確定申告において所得から控除できますが、知らずに年末に掛金払込証明書が届いても捨ててしまい、控除を受けていない方がいるようです。
e-Taxを利用した確定申告では、掛金払込証明書の添付を省略できますので、諦めずに控除するようにしてください。
株の配当をもらった場合
投資している上場株式等の配当の支払いを受ける際、ほとんどの方は源泉所得税徴収されて課税関係は終了し、確定申告は行っていないとおもいます。
しかし、次のようにあえて確定申告することで所得税を減少させることができる場合があります。
総合課税申告をして配当控除を受ける
配当所得と他の所得と合わせた課税総所得金額が1000万円以下の場合、配当所得の10%(住民税2.8%)相当額を税額から控除することができます。
所得税率20%が適用される納税者(課税所得695万円以下)の場合、住民税10%と合わせ税率30%が配当所得にもかかることとなります。例えば、50万円の配当をもらった人の確定申告をすべきかどうかの判断は、次のようになります。
1. 配当所得にかかる税額 50万円×30%=150,000円
2. 税額控除額 50万円×12.8%=64,000円
3. 1.-2.=86,000円
4. 天引きされた源泉所得税額 50万円×20%=100,000円
上記の条件の場合、総合課税の確定申告をして配当控除により税額控除を受けたほうが、納税額が少なく済むことがわかります。
株の売却損が出ている場合の配当との損益通算
上場株式等の配当所得の他に、その所得額を超える売却損がある場合には総合課税の配当控除を受けるよりも、申告分離課税による確定申告をおこない、売却損と配当所得を損益通算するほうが有利となる可能性があります。
なお、証券会社で手続きを行うことで特定口座内で損益通算をしてもらい、残りの所得があれば源泉徴収が行われる制度もあります。
生活用の資産に損害が生じた場合
通勤用自動車が盗難に遭った、災害で家屋が一部損壊した、横領により資産を失ったなどの場合、一定金額を所得から控除することができます。対象資産は、プライベートの生活で通常必要な資産とされ、商品や事業用の固定資産などは該当しません。
控除できる金額は、次のいずれか多いほうの金額となります。損害額を証明する資料などは、税務署に提出を要するため保存をしておきましょう。
(1) 損失額(保険金マイナス後)- 所得金額(分離課税の所得含む)× 1/10
(2) 災害関連支出の金額(後片付け費用など)- 5万円
あとがき
所得税の確定申告では、所得から控除できる配偶者控除や保険料控除、税額を減らすことができる住宅ローン控除などは、知っておられる方が多いと思いますが、他にも節税につながる控除や損益通算などがありますので、検討を怠ると損をしてしまうことが出てきます。
税率の高い方は、特にご自身に適用可能な制度がないか、又どちらの制度を利用したほうが有利かをよく検討することで、節税効果を大きく享受できる可能性があります。
ただ近年では制度が複雑となっているため、よくわからないという方もいらっしゃると思います。そんなときは是非税理士にお任せください。(完)